#07 蓮見翔さん対談まとめ
- Update:
- 2025.09.14
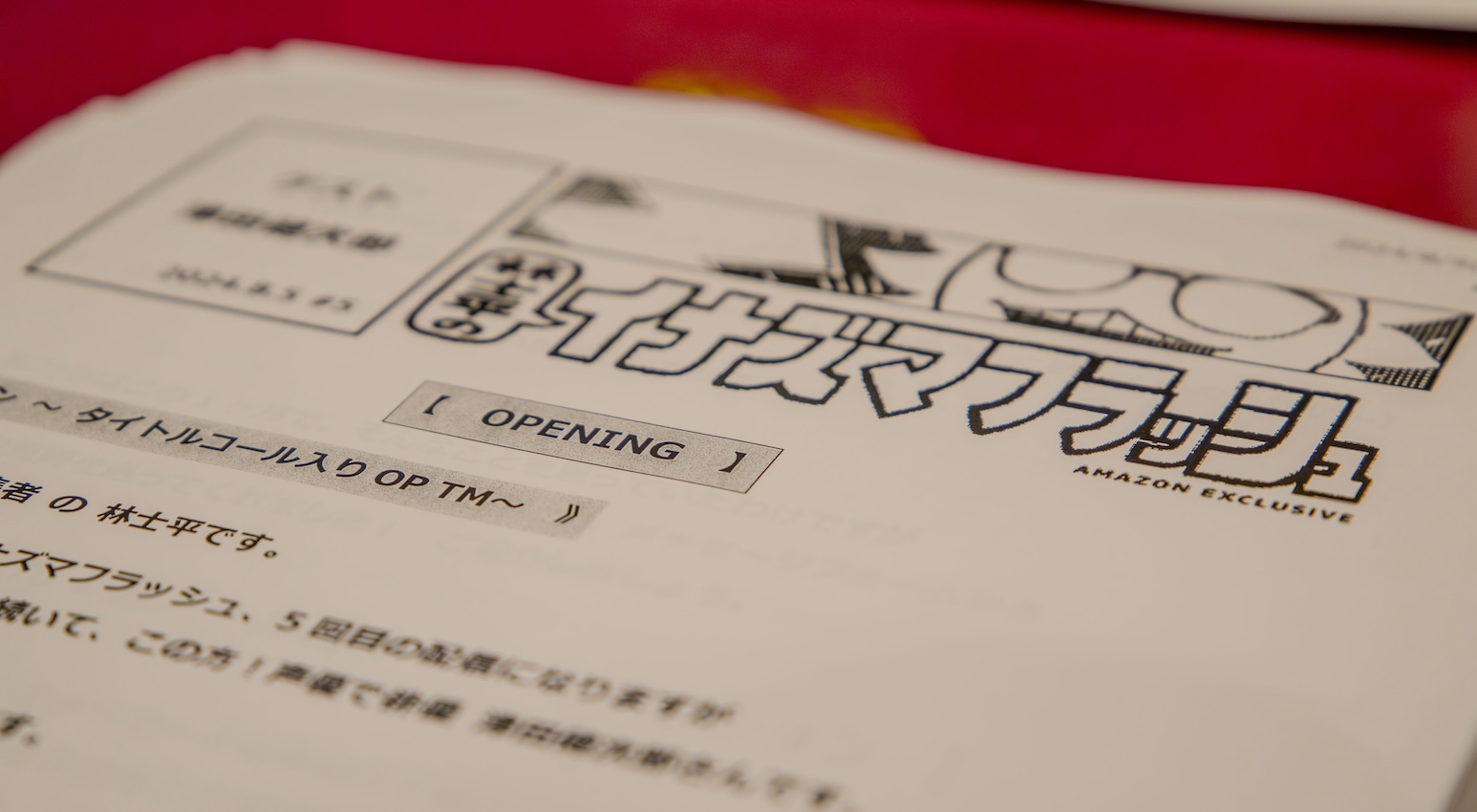
対談まとめ レポート


- Update:
- 2025.09.14
このページでは、各ゲストと林士平さんの対談の内容を、トピックごとにまとめて掲載しています。全8回の対談終了後、二人が話してきた内容や話題に上がった作品を振り返りながら、トップランナーの脳内を覗き見しましょう!

今回はイナズマフラッシュ収録レポート特別編!
コント・演劇ユニット「ダウ90000」主宰で、脚本家・演出家の蓮見翔さんとお届けした、全8回をトピックごとに振り返っていきます。

-
出会いと関係性
蓮見さんと林さんの出会いは、2025年1月に開催された映画『ルックバック』のトークセッション。そこで連絡先を交換した後、ヒップホップトリオ『Dos Monos』のラッパーであり、Podcast番組『奇奇怪怪』のパーソナリティとしても活躍されている、TaiTanさんと3人で食事に行くことに。
蓮見さんは林さんの仕事量の多さと、それをアピールしてこない不気味さに「やばい人だ」と感じたらしく、そこからもっと喋りたくなったとのこと。
二軒目まで行くほど盛り上がり、確かに仲良くなったはずの二人。だったのですが…かなりお酒が入っていたようで距離感がリセットされていると、番組プロデューサーの石井さんから鋭くツッコミを入れられていたのが印象的でした。
吉祥寺出身の林さんと花小金井出身の蓮見さん、地元が近所ということで、近い文化圏で生きてきたのではという話題も。TSUTAYAやディスク・ユニオンなど、平成の景色で盛り上がる二人。
また、お笑いコンビ・かもめんたるの岩崎う大さんもその付近が出身とのことで、もしかしたらコントや演劇のカルチャーを醸成する空気感のある地域なのでしょうか…?
-
演劇へのまなざしと環境の変化
演劇とコントの違いに触れつつ、脚本を書き続けるための工夫や、作り手としての責任を語る姿に、当事者としての真摯な思いを感じました。
ダウ90000第7回演劇公演『ロマンス』は即完売の人気ぶりで、配信も予定されているとのこと。そこから配信の形態についての議論が広がり、独占配信と複数プラットフォーム展開、それぞれのメリット・デメリットを話していく中で、これからは販路設計や周知までの導線が重要になるというお話に。
フェリーの移動中に船内Wi-Fiでのみアクセスできる漫画配信サービスが、すべて1巻しか読めなかったという蓮見さんのエピソードもありましたが、結局蓮見さんも後ほど購入して読んでいるので、導線としては大成功。
短く切ったお試し版や、連休・移動といった余白に届くタイミングでの施策は、知ってもらう機会を最大化するうえで有効なのかもしれません。

-
脚本術と舞台・コントの設計
蓮見さんは、最初からテーマを掲げるのではなく、書いていくうちにキャラクターから立ち上がってくるものをテーマとする型を取っていると語ります。
「情けなさとみっともないプライドが同居する男」が繰り返し登場し、その一貫性が観客の納得に繋がっていく。逆に、ある登場人物が物語のために生きているように見えてしまう瞬間は冷める、という戒めがあるとのことで、蓮見さんの作品の自然過ぎる会話のクオリティの理由が少し見えてきます。
舞台づくりでは、幕で隠すよりもあえて見せておく意識で、開演前から観客に見えている舞台セットに、一番ワクワクするものを置いているそう。例えば『ロマンス』ではジャングルジムを舞台に設置し、観客が想像を膨らませ、本番で裏切ることで体験を最大化したと教えていただきました。
コントについては大きな裏切りから、小ボケやシチュエーションを積み重ねて構成していきます。ときには言わせたい台詞から逆算して関係性や場面を組み立てることも。『ピーク』というコントにおいては、「今、人生で一番楽しいからほっといてくれ」という台詞を輝かせるために構成を整えていったとのこと。
さらに、ネタの精度を上げる工夫についての話題では、自分たちのことを知らない高校生の前で披露した7分のネタを録音し、反応の薄い部分を削った結果、4分の『ベランダ』が完成。賞レースでは分かりやすさを担保しつつも、自分たちの言葉を盛り込み、かつダウ90000の場合は編成人数の使い分けも意識しています。
「大げさな台詞ほど声量を落とす」という演出のこだわりも。嘘のない言葉と行動の整合性に気を使いつつ、不器用さから生まれるズレを笑いにつなげる蓮見さんの価値観が伝わってきた一幕となりました。
-
興味と生活からのエピソード
リスナーさんから頂いた「仕事以外で一番興味のあることは?」という質問に、蓮見さんはギターと即答。お父様がギタリストということもあり、あえて避けていたような面もあったそうですが、家族で出かけた際についに1本購入。
「出会いだから、目に入って良いと思ったものを」と背中を押され、後日には、お父様が使っていないアンプ一式を自宅まで届けてくれたという、何ともほっこりする流れ。「おもちゃだと思って遊べよ」という一言も、蓮見さんのお父様だなと妙に納得感のあるエピソードでした。
ただ、執筆期はまとまった練習時間が取りづらいという悩みも。毎日5分でも触る、音楽仲間に時々見てもらうといった方法でなんとか継続しているそうで、ダウ90000や蓮見さんの活動でギターが交わってくる世界線もあるかもしれません。
一方、林さんの興味の対象は「メモのやり方」。長年ツールを乗り換え続け、Evernote、iPhoneのメモ、付箋、Notionと変遷した末、最近はマークダウン方式で書けてリンクやタグで思考を結べる「Obsidian(オブシディアン)」にハマっているそうです。
マークダウンでテキストを管理して、フォルダリングやAIを使った要約など、カスタマイズ性の高いサービスで、2025年に入って話題になってきている印象があります。
日々の出来事をデイリーノートにひたすら書き出し、後で結び直すことで自分の興味の濃淡が見えてくる、という使い方をしているそうで、そのために数ヶ月データを貯めているのすら楽しそうな様子が伝わりました。

-
記録と体験、そして子育て
個人的に印象的だったのは蓮見さんの「過去飲み」と「未来飲み」という切り分け。どうやら巷には蓮見翔という、可能性が無限大の若者の未来についての話を酒の肴にしている不届き者が居るようです。
過去の思い出は当然、新しく増えることは無いわけで、エピソードは話すたびに強化されていってしまいます。そんな空気を変えるように、蓮見さんの友人が持ってきたのは昔使っていたiPhone。場が一気に盛り上がったとのことで、どんどん記憶や思い出といったものが残りやすい時代になっているのかもしれません。
林さんの、スマホがなかった時代の映像を見て、誰もスマホを構えていない様子に“良さ”を感じたという感想から、スマホを手に持って撮ることによって、その体験が画面越しになってしまっているのではないかという、現代を生きる我々全員に刺さる問いについて話していきました。
RIP SLYME『熱帯夜』のミュージックビデオを真似て学生たちが学校を練り歩く動画など、その瞬間だけの現代では絶対に撮れない“良さ”があるのです。(ちなみにこの収録後には続編とも言える、社会人となった学生たちが、改築された校舎を練り歩く動画が公開されました!)
二度と戻れない瞬間だからこそ、映像や画像に残したい。一方で二度と戻れないからこそ、全力で体験すべき。どちらも間違いではない一方で、逃している何かがある気がしてしまいます。
子育ての中で「最後のハグ」「最後のほっぺへのキス」「最後に手をつないでくれる日」をいつ迎えるのかドキドキしているという林さん。反抗期との向き合い方では、親が理屈で詰めすぎないこと、子が安心して反抗できる環境作りも必要かもしれないという話題も。
心理学的には反抗期はあった方がいいらしい、という情報から、「もし反抗されたら喜んじゃうかもしれないですよね」という林さんに対して、蓮見さんから「早めに動け!統計学からズレろ!」と林さんのお子さんに対しての激励(?)が送られる一幕も。

-
雑誌『東京』を作る
最終回恒例、林さんとゲストと一緒に進めていく企画のお話では、雑誌制作のアイデアが構成されていきました。
元々人生において、どこかで雑誌を作ってみたかったという蓮見さん。「とんでもないカルチャー雑誌を作りたいです」というパンチラインも飛び出し、インタビュー・写真・ポエムなど特定のカテゴリに縛らず全部混ぜの自由気ままな内容で、作り手の遊び心がしっかりと反映されたものを目指します。
年4作の季刊誌なら楽しめるのでは、という実際に月刊誌に携わっていた林さんの知見も入りながら、少しずつ輪郭を帯びてくる雑誌構想。
スタジオジブリが発刊している、小冊子『熱風』のように本当に欲しい人に向けて、クオリティの高いものを作ってみたいというお話も。『熱風』とはスタジオジブリが毎月無料で発行している雑誌であり、非売品。ジブリと関係のある場所や、配送を希望する個人にだけ届いているマネタイズを無視したアウトプットなのです。
高校生向けや30~40代向けの雑誌は浮かぶものの、28歳が買いたいと思う雑誌が意外とない、というイメージも合わさり、夢の雑誌のタイトルは『東京』に仮決定。大人たちの本気の同人誌というイメージで、豪華クリエイター陣がそれぞれ均等な立場で、ページを担当して作っていく……。
部屋に置いて飾りたいと思える表紙や、東京というテーマをどのように落とし込んでいくのか。20世紀最後に生まれた世代の「とんでもないカルチャー雑誌」が刊行される日も、そう遠くないかもしれません…!
ということで、今回は簡易的にですが、ゲスト「ダウ90000」主宰の蓮見翔さんでお届けした、全8回をトピックごとに振り返っていきました。
個人的に印象的だったのは、蓮見さんのコミュニケーション能力の高さと、二人の間に漂う深いリスペクトでした。
世代の違うお二人ですが、何気ない会話の端々に、お互い仕事と真摯に向き合い続けてきた姿勢と、日常にある小さな体験を大切にするまなざしが浮かび上がります。芸人さんということもあり、笑いの絶えない対談となったことも印象的でした。
次回もぜひ番組とこのホームページでお楽しみください。