#49 カンヌ国際映画祭で感じた日本映画の強みと課題
- Update:
- 2025.06.16

山田兼司 映画・ドラマプロデューサー


- Update:
- 2025.06.16
Tyken Inc. CEO 映画・ドラマプロデューサー。慶應義塾大学法学部卒。ドラマ「BORDER」シリーズ、「dele」などを手掛け、東京ドラマアワード優秀賞を2度、ギャラクシー賞を3度受賞。また、仏カンヌでは「dele」でグランプリを受賞。映画「怪物」でカンヌ国際映画祭脚本賞、クィアパルム賞の2冠。「ゴジラ-1.0」では北米の邦画興行収入歴代1位を記録し、史上初のアカデミー賞視覚効果賞を受賞。同年、個人として「怪物」「ゴジラ-1.0」で2つのエランドール賞と藤本賞を受賞。北米では2023年を代表する「アジアゲームチェンジャーアワード」をグラミー賞受賞アーティストのアンダーソン・パークらと共に受賞した。2024年よりPGA(Producers Guild of America)の正式会員に選出。最新の企画・プロデュース作は「ファーストキス 1ST KISS」。

イナズマフラッシュの収録レポートをお届けする本ページ。
今回は番組6人目のゲストとして、映画・ドラマプロデューサーの山田兼司さんをお招きして録音された、#49収録の様子をご紹介します。

二ヶ月の期間を空けて再会となった二人。この間も山田さんは『8番出口』で第78回カンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門に正式招待され、現地参加するなど大忙しの様子。
ちなみにミッドナイト・スクリーニング部門とは、映画祭期間中深夜に特別上映される枠で、アクション・スリラー・ホラー・ドキュメンタリーなどジャンルを問わず、大胆で独創的な作品が選出されやすいと言われている部門。これまでにも『新感染 ファイナル・エクスプレス』(2017)や『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』(2024)など、注目作品を輩出してきました。
山田さんいわく「カンヌは熱海っぽい」そうで、映画祭期間であることはもちろんですが、観光地であることも相まって人が多く疲れることも多いとか。ちなみに映画祭で言うと、サンセバスチャンが美食の街ということで、あらゆる映画関係者が行きたがる街だそうです。世界で何人が参考にできるのか分からない、ハイコンテクスト過ぎる世界の情報でした。

2年前の第76回カンヌ国際映画祭では、『怪物』で脚本賞および日本映画史上初のクィア・パルム賞を受賞している山田さん。林さんから「カンヌをとるコツは?」という、あえてのざっくりした質問も飛び出します。
これに対して「1回目で選ばれて1回目でとれたから…」という最強の謙遜をしつつ、山田さんが挙げたのが「圧倒的な個性」というものでした。横並びで陳列された際に、浮かび上がるために必要な圧倒的なコンセプト力。それもただコンセプチュアルなだけでなく、連綿と続く映画史の中で、極めてオリジナリティのあるコンセプトが無いと、世界的な映画賞レースで勝ち抜くのは厳しいといいます。
しっかりとこれまでの歴史を学び、真摯に賞とも向き合いながら、映画というアートフォームに集まっているメーカーたちが大きなリスペクトを抱き、作り上げていく作品が一堂に介する有名映画祭。その中でピックアップされたり、賞を得たりするためには、並々ならぬ覚悟でないと太刀打ちすら出来なさそうです。
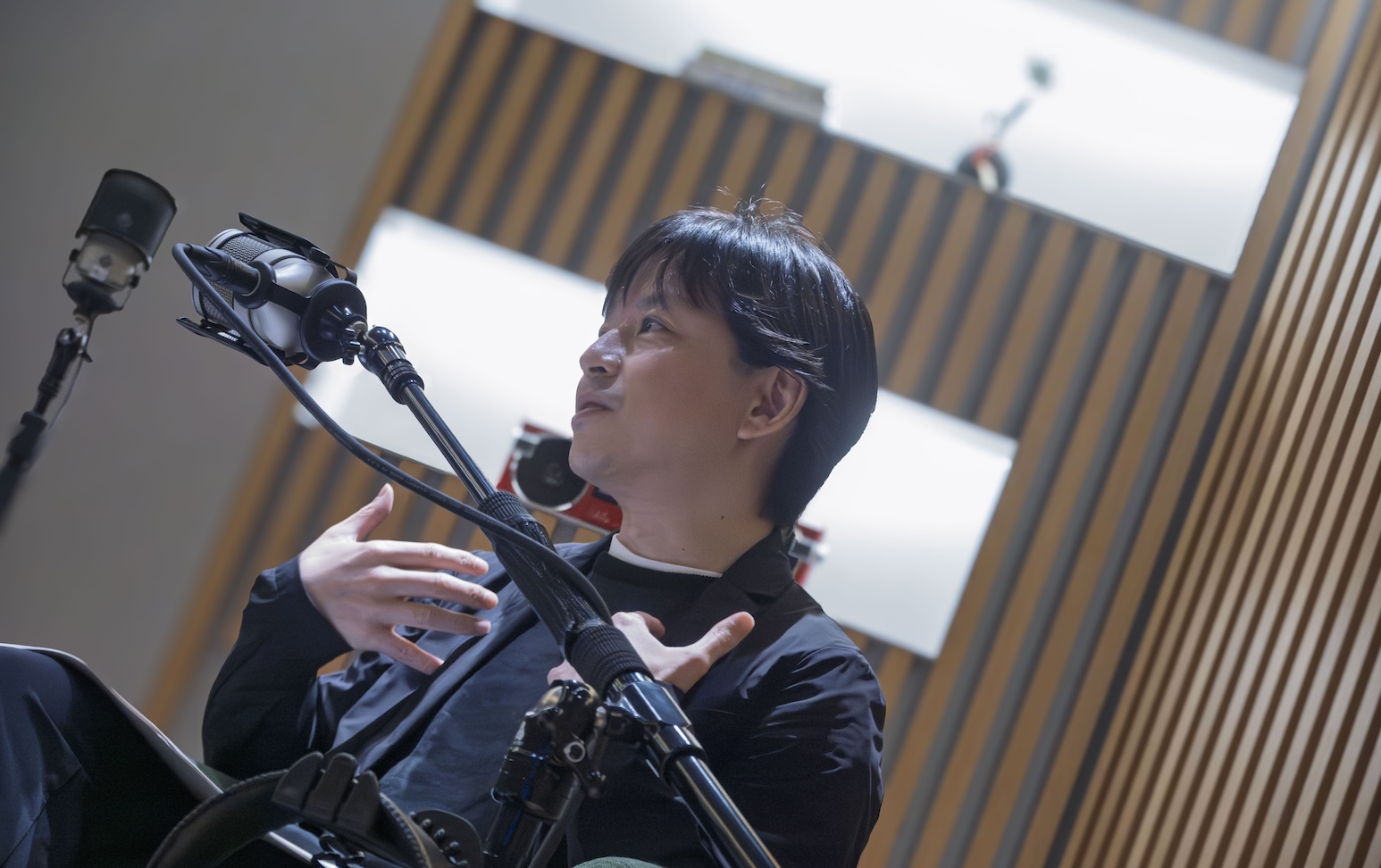
現地で世界の映画祭のディレクターたちと交流していく中でも、日本映画にはとてつもないレガシーがあるから、その財産を大切に勉強してくださいとハッキリ言われたと山田さん。日本の映画の歴史は、世界的に見ても古く、全盛期は1950年代とも言われています。1958年には年間の映画館来場者数が累計11億3千万人にものぼり、当時の人口と比べてみると、国民全員が月に1回以上映画館を訪れていた計算に。
その後、緩やかに縮小していく日本の映画産業。理由は複雑に様々な要素が絡み合った結果かと思われますが、山田さんからは日本が戦後の混乱に陥る中、作り手たちに撮るべきテーマが沢山あったからではないかという意見を頂きました。
日本の三大巨匠とも言われる、小津安二郎、溝口健二、黒澤明の3人。彼らが同時期に現れ、戦後の混乱から高度経済成長期へ向かっていく強いモメンタムの中で、たくさんの作品制作に携われたということも大きな要素でしょう。今見てもとんでもない傑作ばかりであり、その傑作を母国語で味わえるのは、世界で非常に限られた存在ということでもあります。見ていない方、今週末は日本映画の歴史を追ってみるのはいかがでしょうか。

テクノロジーや新たなプラットフォームの登場により、昔の作品へのアクセスもしやすくなった現代。今の若手クリエイターたちは新しい挑戦やチャレンジを求めますが、パソコン一つで黒澤明が見られる時代だからこそ、過去の名作を参照するべきなのかもしれません。
インスピレーションの元は常に歴史の中にあると山田さん。現代を生きているフィルムメーカーは、その歴史を細かく観察し新しいレシピの元を探し、それを現在とコンバインすることで作品を生み出している感覚があるそう。
林さんもカンヌに行くべきというお話になったところで、早々にお時間に。なかなか知ることの出来ない、海外の映画祭について聞いていく回となりました。次回はリスナーの皆さんからいただいたメールも紹介しつつ、映画における宣伝の手法やクリエイティブと働き方改革など、更に二人の経験則も踏まえた対談をお送りします。
ぜひ番組とこのホームページでお楽しみください。